�G�R����(�ȔR��Z�A�ȃG�l�J�[���[�X)�Ƃ́A���߂�ꂽ�R�[�X�ɂ����Ĉ��̋����𑖍s���A�����ɏ�����R�������Ȃ������������̂ŁA�䂪�����o�ꂵ�Ă���uHonda�G�R �}�C���b�W �`�������W�S�����v(2009�N�x�܂ł̑��̂�Honda�G�R�m�p���[�R��Z�S�����)�́A��500�`�[�����Q�����鍑���ő�K�͂̋��Z��ł��B���̑��̎�ȃ��[���́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B
�����́u�c�C�������N���Ă��v
2010�N�x�ɊJ�Â��ꂽ��ȍ������͉��\�̂Ƃ���ł��B�G���g���[�䐔�́A�C���^�[�l�b�g��Ɍ��J���ꂽ������ɐ��v�������̂ł��̂ŁA�ԈႢ�����邩������܂���B�܂��A���̑��ɂ����������邩���m��܂��A�C���^�[�l�b�g�ł̌����Ō������Ȃ����������ŁA�����Ɍf���Ȃ������̂͑��ӂ�����킯�ł͂���܂���B���̓_��e�͉������B
�����̑��̂����A�䂪�����o�ꂵ�����Ƃ�����̂́uHonda�G�R �}�C���b�W �`�������W�S�����v�����ł��B1999�N�x��1���uHonda�G�R�m�p���[�R��Z���k���v�ɏo�ꂵ�����Ƃ�����܂����A�G���g���[�䐔�����ȉ߂������߂Ȃ̂��A���N�O�ɂȂ��Ȃ��Ă��܂��܂����B1992�N�x�ɏ���JT�����J�����Ă������́A�����͗鎭�T�[�L�b�g�ŊJ�Â���Ă����u�}�C���b�W�}���\���v�ɏo�ꂵ�������̂ƍl���Ă��܂������A2000�N�x���Ō�ɂ��̑���������Ă��܂��܂����B�鎭�ł͌��݁A�uHonda�G�R �}�C���b�W �`�������W�鎭���v���J�Â���Ă��܂��̂ŁA�u�����́v�Ƃ����v���͂���܂����A�������˂���͉��߂��āA���܂��ɉʂ������ɂ��܂��B�����Ƃ��A�䂪���̃}�V���́u�c�C�������N���Ă��v��n���̗��K��̕��R�ȃI�[�o���R�[�X��z�肵�ĊJ������Ă��܂��̂ŁA��R�[�X�ƌ����Ă���鎭�Ŋ����ł���̂��肩�ł͂���܂���B�܂��A���ꗬ�`�[�����Q�킵�Ă���uSupermileage Car Challenge Hiroshima �v������̑��݂ŁA���Ј�x�o�����ĕ������Ă������������Ɗ���Ă͂�����̂́A�鎭���������ŁA��������̍H�ʂ������ʂ����S�������܂���B
�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ���A�䂪���ɂƂ��āA�uHonda�G�R �}�C���b�W �`�������W�S�����v�́A�N��1���A���������̓w�͂̐��ʂ��������Ƃ��ł����ɂȂ��Ă��܂��B
|
��� �� |
�� | �J�� | ��� |
�K�� ���s���� (km) |
�K�� ���ϑ��x (km/h) |
�G���g���[ �䐔 |
| 21 | NATS�t�ȃG�l�J�[���Z�� | 6��5�A6�� |
��t�����c�s ���h�w���ENATS�T�[�L�b�g |
12.135 | 24 | 26 |
| 24 |
Honda�G�R �}�C���b�W �`�������W �鎭��� |
6��19�� |
�O�d���鎭�s �鎭�T�[�L�b�g�E���R�[�X |
17.616 | 25 | 114 |
| 14 | Supermileage Car
Challenge Hiroshima |
8��21�A22�� | �L�����L���s �L�����^�]�Ƌ��Z���^�[�E�����̌��R�[�X |
18.513 | 25 | 14 |
| 2 |
Honda�G�R �}�C���b�W �`�������W ������� |
8��28�� |
�Ȗ،��Ζؒ� �c�C�������N���Ă��E���R�[�X |
14.610 | 25 | 75 |
| 5 | ���Ȃ���G�R�J�[���Z��� | 8��28�� |
�_�ސ쌧���{��s ���Y�����ԒǕl�H��EGRANDRIVE |
16.4448 | 25 | 18 |
| 4 | �G�R�}���\������ | 9��18�A19�� |
���쌧����s �G���E�G�[�u |
�H | �H | 30 |
| 21 | ���莩���ԏȔR��Z��� | 9��20�� |
�{�錧���s �{�錧�^�]�Ƌ��Z���^�[ |
�H | �H | �H |
| 19 |
��錧�����w�Z �ȃG�l�J�[�R��Z��� |
9��26�� |
��錧�Ђ����Ȃ��s �����I�[�g���e�B�u�V�X�e���Y�E�e�X�g�R�[�X |
��10 | 25 | 13 |
| 30 |
Honda�G�R �}�C���b�W �`�������W �S����� |
10��9�A10�� |
�Ȗ،��Ζؒ� �c�C�������N���Ă��E�X�[�p�[�X�s�[�h�E�G�C |
16.389 | 25 | 449 |
| 10 | Econo Power in Gifu | 10��31�� |
�����ΌS��j�� ���{���C�������Ԋw�Z�E���݃R�[�X |
5.672 | 20 | 41 |
| 18 | �������Z���G�R������� | 11��13�� |
�É����É��s �É����É������Ԋw�Z�É��Z |
�H | �H | 9 |
| 26 |
Honda�G�R �}�C���b�W �`�������W ��B��� |
11��20�A21�� |
�F�{���e�r�S��� HSR��B�E�T�[�L�b�g�R�[�X |
6.970 | 25 | 45 |
��1�D�d�C�����ԓ��̋��Z�����Â������ɂ��ẮA�G���W���E�G�R�����̃G���g���[�䐔���L�ځB
��2�D�uHonda�G�R �}�C���b�W �`�������W�v�́A2009�N�x�܂ŁuHonda�G�R�m�p���[�R��Z�v�B
�K�\�����G���W���͈�ʂɁA�X���b�g��(�A�N�Z��)�J�x���傫�����A�����M����*1���傫���Ȃ�܂��B���̂��߁A�R���ǂ�����ɂ́A�G���W�����X���b�g���J�x���傫�������ł݂̂œ������悤�ɂ���Ηǂ�*2�̂ł����A�������������ŃG���W���������Ă���ƁA�K�v�ȏ�ɑ��x���㏸���Ă��܂��܂��B
�����ŃG�R�����ł́A���}�Ɏ����悤�ɁA�X���b�g���J�x�̑傫�������ŃG���W�������ĉ������A������x�܂ŒB����ƃG���W�����~���đĐ����s�Ɉڂ�A�������x�ɂȂ�ƍĂуG���W�����n�����ĉ������n�߂�Ƃ������s�p�^�[�����g���܂��B
��*1�@�����M�����Ƃ́A���������R�����{�������M�ʂ̂����A�N�����N�V���t�g������o����d��(�����d��)�̊����B�����d���́A�R�ăK�X(�̈���)���Ȃ��}���d������A�z�r�C�o���u�̋쓮�Ȃǂɗv����@�B���C�����d�������������̂Ȃ̂ŁA�����M���������コ���邽�߂ɂ́A�R�Ă��̂��̂̉��P�����łȂ��A�e���̖��C�����̒ጸ���}��K�v������܂��B
��*2�@���̂悤�ȏ����ł̂݃G���W���삳���ĔR���ጸ���Ă���̂��A�g���^�̃n�C�u���b�h�J�[�u�v���E�X�v�ł��B�u�v���E�X�v�ł́A�A�N�Z����]�蓥��ł��Ȃ������ł́A�G���W���삳�����A�d�C���[�^�ŋ쓮����悤�ɂ��Ă��܂��B�܂��A��������������ݍ����x�ł́A�h���C�o�[���v�����Ă�������x�ɉ����ăG���W���삳���Ă��܂��M�������Ⴂ�̂ŁA�v�������x������������傫�ȃX���b�g���J�x�ŃG���W���삳���A�]�蕪�Ŕ��d�@���ăo�b�e���̏[�d�ɓ��ĂĂ��܂��B
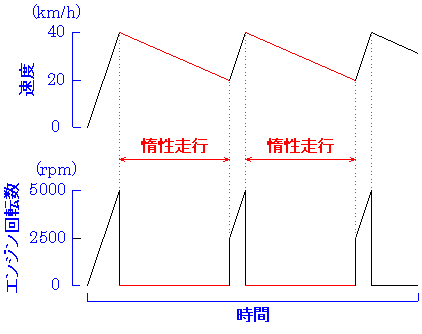
�����ƑĐ����s���J��Ԃ����s�p�^�[���̈��
�R��̗ǂ����Ƃ�W�Ԃ��Ă���s�̎Ԃ̍L���Ȃǂ����Ă���ƁA�u�G���W���̉��ǂɂ��R������コ���܂����v�Ƃ���������������ł��܂��B���̂��߁A�G�R�����J�[�̔R��͂قƂ�ǃG���W�����\�Ō��܂��Ă��܂��ƍl���Ă�����������������悤�ł����A����͈Ⴂ�܂��B
�䂪����1993�N�x�ɏ��o�ꂵ���Ƃ��̋L�^��200km/L���x�ł����B�G�R�����̐��E�L�^�͌���4000km/L�ɂ��B���Ă��܂����A���E�L�^�`�[���̃}�V���̃G���W���̐����M�������A�����̉䂪����20�{�ɂ��B���Ă���̂ł��傤���B�����A�K�\�����G���W���̐����M�����́A�ŗǂ̏����ʼn^�]�����ꍇ��30%���ƌ����Ă��܂����B�����̉䂪���́A�R��̗ǂ��Œm���Ă����u�X�[�p�[�J�u�v�̃G���W����S�������炸�g�p���Ă��܂������A�X���b�g�����i���ĉ^�]���Ă��܂������A�������S�����Ă��܂���ł����B���̕������������āA����10%�ɂ܂ň������Ă����Ɖ��肵�Ă��A����20�{�ƌ�����200%�̐����M�����ɂȂ��Ă��܂��܂����A����Ȃ��Ƃ͕����@���̏ォ�炠�蓾�܂���B�ł́A����20�{���̔R��̈Ⴂ�̂ł��傤���H
���n���s���̔R��(km/L)�́A�ׂ����_���ȗ�����A�ȉ��̎��ŕ\�����Ƃ��ł��܂�(��͔��Ƃ����Ӗ��ł�)�B
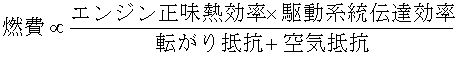
���̂����A�]�����R�Ƌ�C��R�́A
![]()
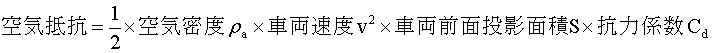
�ŕ\����܂��B25�{���̔R��̈Ⴂ�́A�G���W���̐����M�����̈Ⴂ���������ł��傤���A������2�̒�R�̍��ɂ��Ƃ��낪�傫�������̂ł��B
���̂����]�����R�́A�ԗ�����m�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�y�ʉ����d�v�Ȃ��Ƃ͂����Ɍ��Ď��܂��B�������A�����Ɍy�ʉ�����ƁA�ԗ��̍����s���ő��s�ԗւ̃A���C�����g�������āA�������ē]�����R�W����r�������ē]�����R������������肩�A�M�����̒ቺ���烊�^�C�A�̊�@���������Ă��܂��܂��B�䂪���ł��ߋ��ɖ����Ȍy�ʉ��Őh�_���Ȃ߂��o��������A�����m�ۂ��ŏd�v������p�����Ăю��߂��Ă���A�R��L�^�����シ��悤�ɂȂ�܂����B�������A���N�̂悤�Ɍy�ʉ��̂��߂̒n���ȓw�͂�ςݏd�˂Ă��Ă͂�����̂́A�䂪���̃}�V���͑��ɏo�ꂵ�Ă�������̃}�V���̒��ł����ς�炸�ŏd�ʋ��N���X�̂܂܂ŁA���̓_�ŋZ�p�͕s���͔ۂ߂��A����������ŊJ���邽�߂Ɏn�߂��̂��J�[�{�����v���W�F�N�g�Ȃ̂ł��B
����ɑ��āA�]�����R�W����r�́A�^�C�����G�R������p�d�l�̂��̂Ƃ��A�`���[�u����ʓI�ȃu�`���S��������E���^�����Ɋ�������Ȃǂ̑�ł�����x�܂ł͊ȒP�Ɍ��炷���Ƃ��ł��܂��B�������A�p���N���₷���Ȃ�܂��̂ŁA���s���K�O�ɘH�ʂ𐴑|���邱�Ƃ͕s���ł��B�܂��g�b�v�`�[���ł́A���������g�傷�邱�Ƃɂ��A��w�̓]�����R�W����r�̒ጸ��}���Ă��܂��B
�����C��R�́A�s�̎Ԃł͍������H���s���ɊW���邮�炢�ɔF������Ă��܂����A�G�R�����ł͎ԗ����ʂ����������߁A�]�����R�ɔ�ׂċ�C��R�����ΓI�ɑ傫��(�ԗ����ʂ����������]�ԂŁA��Ԏp���ɂ���đ��s��R���傫���ς��̂Ɠ��l�ł�)�A���ł̕��ϑ��x25�`30km/h�ł͗��҂͓������x���ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B��C��R�ጸ�̂��߂ɂ́A�R�͌W��Cd�����炷���Ƃ��{���I���Ǝv���܂����A���肪��{�̃G�R�����ł͊���o���G�[�V���������삵�Ĕ�r����킯�ɂ������܂���B�܂��A�R�͌W��Cd���ጸ�ł������Ȍ`��̃J�E���삷�邽�߂ɂ́A����ɉ������V���V�̐v���܂߂āA����Ȃ�̋Z�p���v������܂��B���̂��߉䂪���ł́A�`��̉��P�����O�ʓ��e�ʐϒጸ��D�悳���Ă��܂����B����ɂ́A�h���C�o�[�̏�Ԏp�������S�Ȏ��E���m�ۂł���͈͂łł��邾���Q������悤�ɂ���ƂƂ��ɁA�t���J�o�[�h�^�C�v�Ȃ�g���b�h���������邱�Ƃ��̗v�ł��B
�����ɔ�ׂăG�R�����J�[�̎���Ǝv���Ă���G���W���͂ǂ��ł��傤�B�x�[�X�ƂȂ�s�̎Ԃ̃G���W���͂���Ȃ�̊����x�������Ă��܂�����A��݂����ɂ������Ă��R��ጸ�����킯�ł͂���܂���B���s����I�ɂ����邱�ƂŊw�Ԃ��Ƃ�����ł��傤�B�����A�䂪�����o�ꂵ�Ă����uHonda�G�R�m�p���[�R��Z�S�����v�̑��v���ɂ́A�u�Ƒn�I�ȃA�C�f�A�ƋZ�p���������r�̏�ł���v��搂��Ă��邮�炢�ł�����A����͂���ň�T�ɔے肵�܂���B�������A������g���u���͔������₷���Ȃ�܂��B����ł��A�����������̃����b�g���傫���Ɣ��f�ł���ꍇ�ɁA������悤�ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�V���V��J�E���������ɑf���炵�����̂ł����Ă��A�G���W���������Ȃ���ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B
�䂪�����G���W���ɏ��߂Ď����ꂽ�̂�2�N�ڂ�1994�N�x�̂��Ƃł����B�ق�̏��������ꂽ�����������ɂ�������炸�A�S�����2���ڂ̌����X�^�[�g��1���ԑO�ɂȂ��Ă��G���W�����n���ł��Ȃ���펖�ԂɌ������܂����B�ȗ��A�G���W���Ɏ������Γ����قǁA�S�����Ńg���u������������p�x�͑����A���̒��x���[���ɂȂ��Ă����܂����B���������ꂢ�o������A�䂪���ł���Ă�������́A���́u�G�R�����J�[���L�̋Z�p�v�ŗ��Ă��邱�Ƃ��炢�ɂƂǂ߂Ă��܂����B����Ɍ������Z�p���Ȃ��܂܁A�|�e���V�����������グ�邽�߂ɃG���W�����������ă��X�N�����́A�����͒��X�ɂ��ă|�e���V�����������o�����Ƃ��d�����Ă����̂ł��B���̂��߂ɂ́A�����̂��Ղ��͂��Ƃ��A�����������ʂ��Č����ǂ������o�����߂̃h���C�o�[�̕��S�̌y�����������܂���B���������p���ōs���������̂��d�q���䉻�ł��B�������A���ǂ��J��Ԃ������ɁA�G���W���E�G�R�����Ƃ��Ă͂�肷���̃��x���ɒB���Ă��܂��܂����B�d�q���䉻���䂪���̔R��L�^����̈���ł��������Ƃ͊m���ł����A�����Ă��E�߂��܂���B�p���I�ɓd�q�����H�������e�i���X�ł���̐����ۏ���Ă��Ȃ���A�������đ�����������v���ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
�ȏ�̂悤�ɔR��ጸ�ɂ́A�G���W���E�쓮�n���̌��������łȂ��A�]�����R�A��C��R��3�v�f����������d�v�ł��B�������w�͂ɑ�����ʂ͌o���I��3�v�f�Ƃ��������x���ł͂Ȃ����Ɛ��@���Ă��܂��B
�܂��A������3�v�f��Nj����ă|�e���V�����������}�V�����J�������Ƃ��Ă��A�Ō�ɂ��̂������̂͐����͂ł��B�䂪���̂悤�Ȋw���`�[���ł͖��N�����o�[������������ւ���Ă����܂�����A�����͂̈ێ��͑傫�ȉۑ�ŁA���ꂪ�\���łȂ��ƁA�����ɔR��L�^�ɒ��˕Ԃ��Ă��Ă��܂��܂��B�S�����O�̒n���ł̑��s���K���ɂƂ�ƁA�����s�ǂōő�30%���x�R��L�^������������͖����ɉɂ��Ȃ��قǂł����A�A�C�h�����O����ł����ɑ���Ȃ��������Ƃ�����܂����B�������G�R�����̓���ł�����܂����A�ʔ����ł�����̂ł��B
�ȉ��A�G�R�����J�[�ŔR���ǂ����邽�߂ɂ����Ηp�����Ă���Z�p����Љ�܂��B�ߋ��ɉ䂪���ō̗p�����o���̂�����̂Ɍ���܂������A������������Ɏ������Αf���炵���R��L�^���o��Ƃ������̂ł͂���܂���B���`�[���̌�ǂ����Ƃ��Ă��A����Ȃ�Ɏ���H�v���ĐV�@�\���J������̂͊ȒP�ł͂���܂���B����������̂ɁA��肭���삵���Ƃ��̊�т͉����ɂ��ウ���������̂ŁA���ꂱ���G�R�����̊y�����̌��_���Ǝv���܂��B���̈���ŁA�@�\���ЂƂlj�����Ίm���I�ɊԈႢ�Ȃ��M�����͉�����܂����A��ʂɃh���C�o�[�̕��S���������āA���^�C�A�̊댯���͍��܂�܂��B�Y�܂�������ł����A�����́A���ꂼ��̃`�[�����ǂ����߂�R���Z�v�g�ɉ����āA����I�����Ă�����������܂���B�������A��������R�ɑI���ł���̂��G�R�����̗ǂ��Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�G�R�����J�[�ł͑O2�ցA��1�ւ̔z�u�Ƃ��A��쓮�Ƃ���̂���ʓI�ł����A�쓮�ւ̃n�u�Ƃ��ẮA���]�Ԃ̌�֗p�̂��̂��p������ꍇ���قƂ�ǂł��B�������A��փn�u�ɂ̓����E�G�C�N���b�`����������Ă��邽�߁A�Đ����s���ɂ͂��ꂪ�J�`�J�`�Ɖ���炵�Ȃ��瓮�������āA�]�����R��傫�����Ă��܂��܂��B�����ŁA��������������h�����߂ɁA��փn�u�Ɍ�փX�v���P�b�g���Œ肷�邱�ƂȂ��A���҂̊ԂɃh�O�N���b�`��݂���Ȃǂ̍H�v��������̂��ʗ�ł��B
���̋@�\�������������߂Ď����ꂽ�̂�1998�N�x�B�N���b�`���������u�Ԃ̏Ռ��ɂ�鎕�̕ό`���q��̃��x���ł͂Ȃ��A���O�Ɏ����𑝂��v�ύX��]�V�Ȃ�����܂����B�܂����̌���A��փX�v���P�b�g���������ɓ����\�����������߁A�`�F�[���̃e���V��������������A���s���K�i�K�Ń`�F�[���O����o�����܂����B���̂���2002�N�x�ɁA�V�}�m���������ϑ��n�u�̓������������āA�����E�G�C�N���b�`�����R�ɓ��삷�郂�[�h�ƁA�����I�Ƀ����E�G�C�N���b�`��off�ɂ��郂�[�h�Ƃ���ւ�����@�\�ɉ��߂܂����B�����͎蓮�ł������A���N�ɓd�������܂����B
�������A���J�b�v&�R�[�����ŁA�\�������G�Ȃ��Ƃ���A���̍œK�����͓���A�����S���҂���ւ�肷��s�x�A����ɒ��ʂ��Ă��܂����B�����ŁA2012�N�x����A�@�\���̂��̂͏]���^�P���A�n�u�����쉻���āA������J�[�g���b�W��(�[�a�ʎ���)�Ɋ��������@�\�ɉ��߂܂����B
�Ȃ��A2009�N�x�ɘH�ʏ��ǍD�ȗ��K�������ł��邱�ƂɂȂ����̂��@�ɁA�V�}�m���n�u���x�[�X�Ƃ����@�\�̌��ʂׂĂ݂��̂ł����A���ʂ�5%��ɉ߂��܂���ł����B���̋@�\�������̂�2002�N�x�ł������A���̂Ƃ��ɔ�ׂđ��s��R(�]�����R+��C��R)�͔������x�ɂȂ��Ă�����̂Ɛ�������܂����̂ŁA���������̌��ʂ͂�������2�`3%���x�ɉ߂��Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�V�}�m���n�u���x�[�X�Ƃ����@�\�ł́A���C���[����Ă��܂�����A�����������Ă��܂��ƁA�N���b�`��on�ɂȂ�Ȃ��Ȃ��āA���^�C�A��]�V�Ȃ�����郊�X�N�������܂��B���̂悤�ɁA���X�N�̑傫���ɔ�ׂ�ƌ��ʂ͗]��傫���Ȃ����Ƃ���A��փh�O�N���b�`�@�\���̗p���Ă��Ȃ��g�b�v�`�[�������X����܂��B
�������ϑ��n�u���x�[�X�Ƃ�����փ����E�G�C�N���b�`on/off�@�\�̊O��(2009�N�x�^NP��)
�@
�s�̎Ԃł́A�_�v���O�ւ̒ʓd���~���邱�Ƃɂ��A�G���W�����~�����Ă��܂��B�������A�ʓd���~�߂Ă�����A�Đ��ŃG���W���͂��炭��葱���܂�(2009�N�x�ɓ��������f�[�^���K�[�ł̑��茋�ʂɂ��Ζ�2�b)�B���̊ԁA�V�����_���ɋz�������R��(�����C)�́A�R�Ă��邱�Ƃ��Ȃ��A�����r�C�ǂւƗ���Ă��������őS���̖��ʂƂȂ��Ă��܂��܂��B�s�̂̎����Ԃł̓G���W����~�p�x�͏��Ȃ��̂ŁA���������R���̖��ʌ����̉e���͔��X������̂ł����A�G�R�����ł͕p�ɂɃG���W���̎n����~���J��Ԃ����߁A���̉e���͖����ł��܂���B���̂��߃G�R�����J�[�ł́A�z�C�o���u�̓���������I�ɋx�~�����邱�Ƃɂ��A�����C���̂��̂̃V�����_���ւ̋z�����~�����A�Ђ��Ă̓G���W�����~������������Ƃ�̂��ʗ�ł��B��ʂɂ́A�z�C���b�J�[�A�[�����A�J���V���t�g�̎������ɉ����ăX���C�h������Ƃ����ȕւȋ@�\���̗p����Ⴊ�����悤�ł��B�Ȃ��A�d�q����R�����˕����̏ꍇ�A�R�����˂��~���邱�Ƃɂ��G���W�����~�߂�������Ƃ��邽�߁A�z�C�o���u�x�~�@�\�͕s�K�v�ƂȂ�܂��B
���̋@�\�������������߂Ď����ꂽ�̂�1998�N�x�B�����͑��쐫�̈�������h���C�o�[�ɑ���̕��S�������邱�ƂɂȂ�܂������A2003�N�x�ɑS�ʉ��ǂ��Ĉȗ������M�������ւ��Ă��܂���(���C���[�͔N1�炢�̃y�[�X�Ō�������K�v������܂�)�B�������A2008�N�x�ɂȂ��ăJ���V���t�g�̕Ζ��ՂƂ����g���u���Ɍ������܂���(�S�����h�L�������g��2008�N�x�Q��)�B
�z�C�o���u�x�~�@�\�̓����\���ƊO��(2004�N�x�^EG��)
�@
�G�R�����J�[�̔R���������u�Ƃ��čł������g���Ă���L���u���^�[�ɂ́A�]���ȔR�����������Ȃ��悤�Ƀt���[�g�ƘA������j�[�h���o���u���݂����Ă��܂��B�������A�L���u���^�[�̃t���[�g�����̔R�����\���ł��A�U���̂��߃t���[�g���㉺���Ă��܂��A�j�[�h���o���u���J���J��Ԃ��A�]���ȔR�����t���[�g���ɗ��ꍞ��ł��܂��܂��B���������o�ꂵ�Ă����uHonda�G�R �}�C���b�W �`�������W�S������v�ł́A���s�O��̔R���^���N�̏d�ʍ�����R����Z�o����g�b�v�A�b�v���ƌĂ��v�����@���Ƃ��Ă���̂ŁA�t���[�g�����ɗ]���ȔR�����������Ă��܂��ƁA���̕��R��̌v�����ʂ͈������Ă��܂��܂�(�Ⴆ�ΔR���^���N��10g�y���Ȃ��Ă������̂́A1g�̓t���[�g���ɑؗ����Ă����Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B���̏ꍇ�A�{���̔R������ʂ�9g�ł����A���ł̔R��L�^��10g������Ƃ������ƂŎZ�o����Ă��܂��܂�)�B���̂��߁A�R���^���N�ƃL���u���^�[�̊Ԃɓd���o���u��݂��A�Đ����s���͂��̃o���u��close���āA�]���ȔR�������ꍞ�܂Ȃ��悤�ɂ���H�v���l�Ă���Ă���A�����̃`�[����������̗p���Ă��܂��B
���̋@�\�������������߂Ď����ꂽ�̂�2008�N�x(NP���U�̃y�[�W�Q��)�B�ړI�͑��s���K�i�K�ł̔R��v���̍Č�������ŁA���̌��ʂ͐��ł������A����ł��d�q����R�����ˎ��ɔ�ׂ�ƁA�f�[�^�̂���͑傫���A�ԑ̊e���̉��ǂ̌��ʂ𐄂��ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ���A2009�N�x�̑��������ăL���u���^�[������P�ނ��܂����B
�R���J�b�g�p�d���o���u�̓A���~�������̃X�e�C�Ŏx������Ă��܂�(2008�N�x�^NP���U)
�R�ĂɎ��Ԃ�v����ƁA���̊Ԃɂǂ�ǂ�s�X�g�������~���Ă����̂ŁA�V�����_���̗e�ς������Ă��܂��Ĉ��͂��オ�炸�A�L���ɃG�l���M�����o�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���̂��߁A�_�v���O��2�ɑ��₷���Ƃɂ��(�c�C���v���O��)�C�Ή��`�d������Z�����ĔR�Ċ��Ԃ�Z�k���A�M���������コ��������������Ηp�����Ă��܂��B���̕����͂����H�Ɏs�̎Ԃł��p�����Ă���A�G�R�����J�[���L�̋Z�p�Ƃ͌����܂��A�̗p��������l����ƁA�G�R�����J�[���L�̋Z�p�ɉ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
���������n�߂ăc�C���v���O�������̂�1995�N�x�B�������A����ȗ��A�s�X�g���ƃv���O���Ԃ���g���u���ɍĎO�������Ă��܂����B���̓_�̓��O�ȃ`�F�b�N���������܂���B�܂��A�v���O���̒lj��H�͎��s���₷���̂ŁA���O�̏\���Ȍ������K�v�ł��B
�lj��H�������Ƀv���O����������Ŋm�F���Ă���l�q�ƁA�d�オ��B
�@
��ʂɃx�[�X�ƂȂ�G���W���ɂ͋@�B���̃I�C���|���v���݂����Ă��܂����A�I�C���|���v�̋쓮�ɂ���炩�̓��͂͏����܂�����A�R��ɂ̓}�C�i�X�ƂȂ�܂��B�܂��A��ʂɃx�[�X�G���W���͉��u���Ȃ̂ŁA�z�C�[���y�[�X�Z�k�Ȃǂ̖ړI����c�u���ɉ��߂�ƁA�|���v���g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ōl�Ă��ꂽ�̂������ł��B�G�R�����ł̓G���W���͒f���I�ɉ^�]����A���������̉^�]���Ԃ͒Z�����Ƃ���A��������܂łɋ������ׂ��I�C���̗ʂ͂����đ����͂���܂���̂ŁA���ʂ̃I�C�����^���N�ɗ��߂Ă����āA������d�͗������ŃG���W���e���ɋ������邱�Ƃ��ł����(�d���o���u��݂��ăG���W���^�]���̂�������悤�ɂ��Ă���`�[��������܂�)�A�I�C���|���v���Ȃ������Ƃ��ł��A�R��L�^�̌���ɂ��q����܂��B���̂��߁A�����̃`�[���ō̗p����Ă��܂��B
���������n�߂ēH�������̂���ꂽ�̂�1996�N�x�ł����B�G���W�����c�u���ɂ���ƂƂ��ɁA�N�����N�P�[�X�̈ꕔ��؏��������߂ɁA�I�C���|���v���g���Ȃ��Ȃ������Ƃ����������ł����B�������A�[���v�����Ȃ��H�����Ɉڍs�������߁A�K�v�ȉӏ��ɃI�C�����s���n���Ă���Ƃ͌�����A�G���W���̐M�����̑啝�Ȓቺ�������Ă��܂��܂����B�T�[�r�X�}�j���A������������ƌ��Ă���A�ǂ��ɋ������ׂ����͈�ڗđR�������̂ɁA�����ӂ��Ă������߂Ɍ�����ꂽ�g���u���ł����B���̌�A�������͓d���|���v�ɂ��I�C�����������ɉ��߂܂����̂ŁA�H�����̃m�E�n�E�͎������킹�Ă��܂���B
�@
�s�̎Ԃł́A�R�Ď���������ɗ�p���邱�Ƃɂ���āA�m�b�L���O�ƌĂ��ُ픚���ւ̑ϐ������߁A�_�Ύ������œK�����邱�Ƃ��R��ጸ�̃|�C���g�ƂȂ�܂��B�������G�R�����ł́A�G���W�������Ă��鎞�Ԃ��Z�����Ƃ���A�G���W����~���ɂ����ɗ�₳�Ȃ��悤�ɂ��邩���d�v�ƂȂ�܂��B���̂��߁A��p�t�B����؏�������A�V�����_�w�b�h��z�C�ǂȂǂ�f�M�ނŕ������肷��Ȃǂ̉������u�����̂���ʓI�ł��B���ɁA�V�����_��V�����_�w�b�h�̗�p�t�B���̐؏��́A�y�ʉ��ɂ��Ȃ��邱�Ƃ���A�قڑS�Ẵ`�[�������{���Ă��܂��B�܂��A�R�Ď��ߕӂɐ���I�C���𗭂߂��Ԃ�݂��邱�Ƃɂ��A�M�e�ʂ�傫�����āA���x�ω���}������悤�ɂ��Ă����������悤�ł��B
�ۉ��݂̂ɏd�_��u�������āA��p�����낻���ɂ���ƁA�g�@�^�]���ɃI�[�o�[�q�[�g�ɂȂ��Ă��܂��܂�(�S�����h�L�������g��2001�N�x�Q��)�B�����ŁA���݂ł͏����p�Ɨ�p�p��2�̓d���|���v��p����V�X�e���ɉ��߂Ă��܂����A���ꂩ����|���v������s�ǂɊׂ��ăI�[�o�[�q�[�g�ɂȂ������Ƃ�����܂�(�S�����h�L�������g��2006�N�x�Q��)�B
���̊O���Ƀ��W���[�}�b�g���������܂�(2008�N�x�^NP��)
�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂�