2004年度に開発したEG号Ⅱは、GFRP製カウルの装着が前提だったにもかかわらず、カウル製作技術が低下していたため、暫定ペット製カウルで出走させざるを得ませんでした。しかし、2005年度には、カウル製作技術を磨き直す目的で、保管してあったEG号のメス型からカウルを作り直す作業にも成功し、いよいよEG号Ⅱ用のカウルを新開発する技術的基盤は整ってきたものと判断されました。
一方、この頃、電子制御燃料噴射システムを搭載するための基礎検討も進んでいました。2004年10月発売のスズキの50ccのスクーター「レッツ4」に搭載されたミクニ製ディスチャージポンプ(DCP)式燃料噴射システムを購入して調べてみると、エンジンを横置きにするのが望ましいことがわかりました。ところが、当時のマシンはいずれも縦置き仕様で、電子制御燃料噴射システムを搭載するにはシャシを新開発する必要がありました。
そこで、EG号Ⅱは引退させ、その後継機としてエンジン横置き、電子制御燃料噴射システム搭載のニューマシンを開発し、そのマシン用にカウルも新開発することにしました。それがこのNP号です。NP号では、EG号Ⅱで得た技術を継承発展させるべく、
EG号Ⅱをベースに、エンジンを横置きに改めるとともに、トレッドを大幅に縮小し(EG号に対して約100mm)、全高も下げる(EG号に対して約100mm)。
カウルはGFRP製フルカバードタイプとし、極力前面投影面積を小さくする。
ミクニ製ディスチャージポンプ(DCP)式燃料噴射システムを採用する。併せて、電子制御スロットルも組み込む。
従来の総合電子制御回路を発展させて、電子燃料噴射システムの制御も組み込む。
という方針で開発に臨みました。そして、目標として「初年度800km/L、3年目には1000km/L」を掲げました。1000km/Lは、エコラン参戦当初からの夢でしたが、それを開発目標として掲げたのは初めてのことです。
このNP号。従来とはかなり仕様が異なるだけではなく、8年ぶりにGFRP製のカウルを新開発することになったので、完成度の高いマシンを作り上げるには、速やかな設計が必要条件でした。しかし、設計は大幅に遅れ、しかもようやく製作に取りかかったと思ったら、致命的な設計ミスが相次いで発覚するなど、我が部始まって以来のドタバタ劇を繰り広げることになりました。このため、新開発のカウルも含めた全装備での試運転は8月下旬まで縺れこむ有様で、十分な完熟走行は望めず、折からの整備力の低下傾向と相俟って、2006年度の大会はとりあえず完走できれば良しとするしかないと思わされました。
しかし、初回の走行練習から素晴らしい記録を連発し、最後の走行練習では、前年度のEG号の記録を約50%も上回るようになりました。全国大会では、初日にエンジンの始動ができないという過去最大級のトラブルに見舞われましたが、2日目の決勝では936km/Lを記録。走行練習の結果からすれば多少物足りない記録でしたが、初日のトラブルのことを考えれば満足すべき結果だったと言えるでしょう。
2007年度は、新型車のNP号Ⅱの開発に追われたこともあって、
エンジン各部の細かな改良。
燃料噴射時間にバッテリ電圧補償を組み込むための総合電子制御回路の一部改修。
フリクションロス低減のため、ピストン、ピストンピン、ピストンリングにWPC処理&モリブデンショット。
やや剛性不足だったシャシの一部補強。
最低地上高をアップするため、雌型を一部修正した上でのアンダーカウルの再製作(約3.2kgの軽量化)。
ぐらいしか改良を行いませんでした。ただし、前年度十分に調整することのできなかった電子制御燃料噴射システムの真価を発揮させるべく、燃料噴射時間などの調整には時間をかけました。3月までにはこれらの改良、調整もほぼ完了して、残るは走行練習で煮詰めていくだけと思われましたが、4月の下旬頃からトラブルが頻発。このため、この年初の走行練習となった5月12日は、エンジンを始動させるのがやっとという有様で、記録はボロボロ。以来なかなか復調を見せませんでしたが、ようやく8月29日になって本領を発揮。この調子でもう少し煮詰めていけばと思いきや、9月に入ると練習場が使えなくなってしまって、結局そのまま全国大会に臨まざるを得ませんでした。
全国大会では初日の朝からトラブルに見舞われ、何とか出走した公式練習で1028km/Lを記録しましたが、万全の整備で臨んだつもりの2日目の決勝では、電子制御スロットルのトラブルで988km/L。残念ながら1000km/Lの目標達成は果たせませんでした。
2008年度は、「3年目までに1000km/L達成」という開発目標を達成すべく、以下の改良に取り組ました。
前年度の全国大会で発生した熱害に起因するトラブルを解決するため、吸気系統などの改良。
断熱塗料+耐熱パテによるエンジンの断熱強化。
フリクションロス低減のため、シリンダにWPC処理&モリブデンショット。
新規購入したシリンダヘッドを用いた冷却用オイル経路の見直しと点火プラグの突き出し量の変更。
転がり抵抗低減のためワイドリム化(20×2.125)。ただし、タイヤはミシュラン製エコラン用のまま。
双子車のNP号ⅡのGFRP製カウルを移植。
初の走行練習となった6月15日には、満足にアイドリングすらできない惨状を呈しました。以来、エンジントラブルは連鎖的に発生し、走行練習に行っても、データを取る価値を見出せない状況が続きました。整備力が安定して、ようやくまともに走りこめるようになったのは5回目の走行練習となった8月28日になってからでしたが、燃費データは前年度のベスト記録をやや超えるぐらいで、決して大きく超えるものではありませんでした。ただし、前年度はデータのばらつきが大きかったのに比べて、データの再現性は著しく向上しており、信頼性が高まっていることは確認できました。
全国大会決勝では、これまで一度も経験したことのなかった電装系統のトラブルが発生してエンジンが始動できなくなって、スタートラインから一歩も動かないままリタイアとなりました。折から進めていたカーボン化プロジェクトで、我が部初となるCFRPモノコック車両BG号の開発をこの年の全国大会後から本格化することにしていたため、NP号はこの年を最後に引退させることにしていたのですが、有終の美を飾らせることはできませんでした。
ところが、BG号の開発が難航したため、2009年4月になって、急遽NP号を2009年度の大会に出走させることになりました。2008年度の大会終了後、NP号はほったらかし状態になっていたため、全国大会までにどれだけのリファインできるのかは白紙の状態でした。しかし、「3年目」まではともかく、「1000km/L達成」の開発目標にトライする機会が再度到来したわけですから、何とかそれを達成すべく、突貫作業で以下の改良を行いました。
前年度の全国大会で動作不良が発生した後輪クラッチ機構のソレノイドの換装(吸引力強化)。
旋回時の走行抵抗を減らすため、ナックルアーム及びタイロッドの改良。
総合電子制御回路へのデータロガー機能の追加と、それに伴う速度検出応答性の改善。
イグニッションコイルの換装(同時点火タイプからノーマルタイプ2個)とそれに伴うメイン回路の改良。
スロットルの自動open時期をエンジン回転と同期させることにより、それまでの過大だった過渡補正を抑制。
6月14日以来、走行練習を重ねるうちに整備力も安定したこともあって、9月14日にはそれまでの燃費記録の実力値を約10%も上回る好記録を連発。さらに、大会一週間前に行ったシャシローラでの実験では、それまでの良いときの燃料消費量を10%程度低減するデータを安定して叩き出しました。
期待に胸を膨らませて臨んだ全国大会では、公式練習で1213km/Lを記録したものの、事前の想定を遥かに下回りました。そこで、データロガーで採取したデータに基づいて、走行パターンを変更して決勝に臨むことにしましたが、これが仇となり、残り1周の時点で平均速度25km/Lの規定走行時間を20秒もオーバーする事態に陥りました。最後はドライバーが機転を利かせて、何とか規定走行時間内にゴールすることができましたが、後半の無理な走行がたたって1177km/Lにとどまりました。
NP号は、我が部初の電子制御燃料噴射式を採用したマシンでした。当初はキャブレター式の足元にも及ばぬ燃費性能しか発揮できませんでした。エンジン部門の総力を挙げて改良に取り組んだ結果、とうとう2008年度にはキャブレター式に肩を並べる記録を出すようになりましたが、残念ながら全国大会ではリタイア。BG号の開発遅延から、引退時期を1年延ばして出場した2009年度は、地元での走行練習でキャブレター式を上回る燃費記録を連発しました。全国大会の記録には物足りなさが残ったものの、兎にも角にも1000km/Lの開発目標を達成することができました。その感慨は言い知れぬもので、開発当時の熱っぽい雰囲気の記憶とともに、まさに忘れ難いマシンとなりました。
8年ぶりに新開発したGFRP製カウルは、新幹線車両のような形状。空気抵抗低減に絶大な効果を挙げました。ちなみに、塗装はRX-8に使われているウイニング・ブルー・メタリックという色で、いきつけの塗料屋さんに調合してもらったものです。コンパウンドで磨きに磨いたため、ルーフ部分の写真写りが変になっています。なお、我が部では地道な努力を続けてきたカウル製作グループに塗料の選定を任せるのが伝統で、彼らが塗料屋さんで見せていただいた色見本から気に入ったものを選んだらたまたまRX-8に使われているものだったというだけで、ロータリーエンジンを熱愛するエンジン担当で5年生のH君の陰謀によるものではありません。
EG号(左)との比較。全高が約80mm、全幅が約200mm小さくなりました。ただし、DCP式燃料噴射システムを採用した関係で、燃料タンクの位置が高くなっています。
前輪支持部はEG号Ⅱの部品を流用。操舵系統は、EG号Ⅱをベースに、トー調整がやり易いように改良しました。
本校チーム初の電子制御燃料噴射システム。スロットルも電子制御化しました。
メイン回路はエンジンの上に搭載。バッテリも後輪付近のポケットに収納。交換が楽になりました。
EG号が前年度で引退したので、蟹のステッカーはNP号が引き継ぐことになりました。
NP号ⅡのGFRP製カウルを引き継ぐことになりました。トレードマークの蟹も塗装に合わせてモデルチェンジ。
ワイドリム化(20×2.125)しました。ただし、タイヤは2007年9月に販売終了となったミシュラン製20×1.75のままです。まだ使えるタイヤがあるからという経済的な事情もありましたが、NP号Ⅱに装着することになったTGMY Asida製20×2.125タイヤと比較検討したいとの狙いもありました。
エンジン部門では、電子制御燃料噴射システムの吸気系統の改良、シリンダヘッドの交換とともに、断熱強化に取り組みました。断熱塗料を塗布して加熱硬化させた上で、剥離を防ぐため、耐熱パテで覆い尽くしました。しかし、全国大会では電装系統のトラブルでリタイアとなり、その効果を実証することはできませんでした。
イグニッションコイルを、同時点火タイプからノーマルタイプ2個に改めるとともに、ドライブ用のパワートランジスタをIGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)に換装しました。
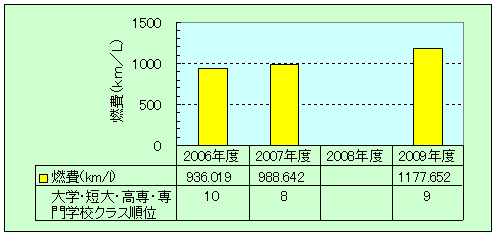
注.2008年度はリタイア。
写真をクリックすると大きくなります