GT���́A�t���[�����A���~�����ɂ��邱�ƂŌy�ʉ���_�����̂ł����A��{�I�ȍ\����JT���Ƃ����ĕς��Ȃ��������߁A�d�ʌy�����ʂ͏��Ȃ��A���̈���ŁA�n�ڕ��̋��x�ɕs�����c��܂����B�����ŁA�t���[�����X�e�����X�|�ɖ߂����}�V���Ƃ���1998�N�x�ɊJ�����ꂽ�̂�EG���ł��B
EG���̖��O�̗R���́AGT���ł�3�����I�ȃL���m�s�[�ɖ������t�����g�E�X�N���[�������t�������߁A�c�݂��Ђǂ��A�h���C�o�[�̑O�����F�������������̂ŁA�������������������邽�߁A2�����I�ȃX�N���[�����Ȃ����t�����悤�ɂ��āA�^�]��easy(�C�[�W�[)�ɂ���悤�Ӑ}�������ƂɋN�����܂��B�܂��AEG���̃J�E���̑��ʐ}�߂Ă�����A�����u�g���^�̓V�˃^�}�S�v�̃R�s�[�Ńx�X�g�Z���[�ƂȂ��Ă����~�j�o���u�G�X�e�B�}�v�̂���ɗǂ����Ă��Ă���悤�Ɏv�������Ƃ���(�����܂Ŏv���������ł�)�A�^�}�S��egg����EG���Ɩ��t������ʂ�����܂��B
����EG���̊J�����j�́A
�Ƃ������Ƃ���ŁA�|�e���V�������炷��A�]���̔��ˍ���}�V���̐�����傫�����������I�ȃ}�V���ɂȂ�͂��ł����B
�������A�J�����x��ɒx���(�J���ɂ������������B�̓w�͂͐q��Ȃ炴����̂��������̂ł���)�A�낭�Ɏ��^�]�����Ȃ��ő����}���˂Ȃ炸�A���̂����G���W���̑g���~�X��ԑ̂̍����s�����d�Ȃ��āA���N�x�̓��b�^�[������284km�̎S�X����L�^�ɏI���܂����B
�@
2�N�ڂ�1999�N�x���A���ljӏ��͋��x�s���������J�E���̕⋭���x�ŁA��Ɨʂ͑O�N�x��1/10�ȉ��������ɂ�������炸�A�J�����x��āA���O�̎��^�]�͂�������1��B���ǁA�ԑ̂̍����s���Ȃǂ̗v���ɂ��366km/L�ɂƂǂ܂�܂����B
�@
�����ŁA2000�N�x�́A��Ƃ��č����A�b�v�Ɏ��g�݂܂������A�܂����Ă��J���̒x��������O�̎��^�]��1���Ƃ����L�l�B�L�^��367km/L�B���N�̂��Ƃł����A���^�]�s���̂��ߊe��ݒ肪�œK���ł��Ȃ��������Ƃɂɂ����̂Ǝv���܂��
�@
2001�N�x�̓}�V���̉��ǂɂقƂ�ǎ�����Ȃ��������߁A�\���Ȏ��^�]�ɂ��A�g���u������������ƂƂ��ɁA�e��ݒ���œK���ł���͂��ł����B�������A�����̕s���ӂ��炱��܂ʼn��̖����Ȃ������ӏ���j��E�j������Ƃ������Ԃ��������A���ǁA�v�����قǎ��^�]�͂ł��܂���ł����B����ł��A����EG���ɂȂ��Ă���Ƃ��ẮA���s���K�ōł��L�v�ȃf�[�^(�_�Ύ����y�ы�C��)�������܂����̂ŁA�������������422km/L�ƁA6�N�Ԃ�Ƀ`�[���L�^���X�V���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@
2002�N�x��4�N�Ԃ�ɑ啝�ȉ����������܂����B��ȕύX�_�́A
�Ƃ������Ƃ���ł��B�������A��N�̗�ɘR�ꂸ�A�}�V���̊J�����x�ꂽ���߂ɁA�d�q�����H�̕]�������Ă��鎞�Ԃ��s�����āA2002�N�x�̑��ł͂���܂ł̉�H�ŗՂ܂���܂���ł����B����ɔ����ď����������H�����̂܂܂Ƃ��܂����B�܂��A�d�����̋z�C�o���u�̒�~�@�\�͖����̂܂ܑ����}���Ă��܂��܂����B
�]���āA���ɊԂɍ������̂́A�^�C���̊����ƃ����E�G�C�N���b�`�@�\�ւ̕ύX�����������̂ł����A�����2�_�̕ύX�Ƃ���ɔ����쓮�n�̌������A�����đO�N�x�܂ł̃f�[�^�̒~�ς�����t���āA���b�^�[������473km��2�N�A���Ń`�[���L�^���X�V���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@
2003�N�x���A�ԑ̂ƃJ�E���͑O�N�x�̂܂܂Ƃ��A��Ƃ��āA
���k��̌���(2000�`2002�N�x�͈��k����m�[�}���̂܂܂Ƃ��Ă��܂������A�v���Ԃ�Ɉ��k����A�b�v���܂���)�B
�z�C�o���u�x�~�@�\�A��փN���b�`�@�\�̃\���m�C�h���B
�O�N�x�ɊJ�����������d�q�����H�y�ѓd���|���v�ɂ�鏁�������̗̍p
�Ƃ��������ǂɎ��g�݂܂����B���s���K�ł́A�g���u�����������M�����̓_�ŕs���͎c�������̂́A�L�^�͑O�N�x��傫�������Ă���A�g���u�������Ȃ���ΑS�������`�[���L�^���X�V�ł�����̂Ǝv���܂����B
�������A�S�����́A�䕗�ڋ߂̕���钆�A�J�Ƃ̐킢�ɂȂ�܂����B�ˊэ�Ƃ̉J����t���Ċ����͂������̂́A�L�^��395km/L�ɂƂǂ܂�A�L�^�X�V�͂��a���ƂȂ�܂����B
�@
2004�N�x�̎�ȉ��Ǔ_�́A
�쓮�����ጸ�̂��߂̒��Ԏ��̎x���@�������y�т���ɔ����V���V�㕔�̑S�ʉ��ǁB
�h�����E�σm�C�Y���E���쐫����̂��߁A�����d�q�����H�̑S�ʉ��ǁB
���C���W�F�b�g�̏��a��(�R�ĉ�)�y�т���ɑΉ�����������ł̓_�ΉΉԂ̋����B
�I�C���R��h�~�̂��߂̏����n���̌������B
�ۉ��̂��߁A�V�����_�w�b�h�̔R�����㕔�̋�ԂɃI�C�����߂����B�܂��A�I�[�o�[�q�[�g�h�~�̂��߁A�������T�[�~�X�^�Ōv�����A��艷�x�ȏ�ɂȂ�����A���̕����̃I�C�����z������悤�ɂ���B
�O�N�x�ɔ��������R�Ď����ւ̃I�C���Z���h�~��B
�Ƒ���ɓn��A�V���V�O���̑O�֎x�����ȊO�͂قƂ�ǑS�č�蒼���A�t�����f���`�F���W�ɋ߂�����C�ƂȂ�܂����B�ɂ�������炸�A�ŏ��̑��s���K��7��5���Ɨ�N���������A���̌�������Ƀf�[�^��肪�i�݁A���K��ɂ����鎩�ȋL�^�����X�ƍX�V���Ă����܂����B�������A���K�ꂪ�����h�ЌP���̂���8�������ς��g�p�ł��Ȃ��Ȃ�A�Z�b�e�B���O���ϋl�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂ܑS�������}���˂Ȃ�܂���ł����B
�S�������͍D�V�Ɍb�܂�A�������K�ʼnߋ��ō���600km/L���L�^���܂������A��]���ĉJ���̑��s�ƂȂ���2���ڂ̌����ł́A���E�s�ǂɋN������g���u�������^�C�A�B2�N�A�����ĉJ�̂��ߋL�^�X�V�͉ʂ����܂���ł����B
�@
2005�N�x�́A
�G���W���̏����ۉ��n���̌�����(�R�Ď����ւ̃I�C���Z���h�~����܂�)�B
�G���W���e���̌y�ʉ��B
�O�֎x�����y�ё��njn����EG���U�Ɠ��l�̃V�X�e���ɕύX�B
FRP���J�E���̘V�����ɔ����āA�ۊǂ��Ă��������X�^����̍Đ���B
�Ȃǂ̉��ǂ��s���܂����B���s���K�ł́A�O�N�x�̗��K��ɂ�����L�^��啝�ɏ��������̂́A�����s�ǂɂ��g���u�����������A�s������@�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��܂ܑS�������}���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B
3�N�Ԃ�ɍD�V�Ɍb�܂ꂽ�S�����ł́A�����ɏ����ȃg���u���������������̂́A2���ڂ̌����ł̓m���g���u����694km/L�B3�N���̉��ǂ̐��ʂ��ꋓ�Ɍ���āA�啝���`�[���L�^���X�V���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@
2006�N�x�́ANP���̐V�J���ɒǂ��āAEG���Ɏ�������Ă���]�T���Ȃ��A
�s�X�g�������ɂ�鈳�k��̍X�Ȃ����B
�^�C���`���[�u�̃E���^�����B
�Ƃ������ȒP�ȉ��ǂ����ł��܂���ł���(���ǂł͂���܂��A�h���C�o�[����10kg�y���Ȃ����̂����\����v��)�B���s���K�ł́A�|�e���V�����̌���͖��炩�Ȃ��̂́A�����͂̒ቺ�ɋN�����āA��������肵�Ĕ��������邱�Ƃ��ł����A���ǂ������v�����������܂����B
�������A�S�����ł�872km/L���L�^�BEG���̉��ǂɖ{�i�I�Ɏ��g�ݎn�߂�2002�N�x�ȗ��C�ł��蔲���̉��ǂ������ɂ�������炸�A�O�N�x�̋L�^���180km/L�������Ă��܂����̂ł��B
���͑��O����AEG���͂��̔N����ň��ނ����邱�ƂɌ��߂Ă��܂����B�ł�����A1998�N�x�ȗ��A���炭���Ă��ꂽEG���ɂ́A�L�I�̔������点�����Ƃ͊���Ă��܂������A����قǂ̋L�^�͑z��O�ł����B
EG���̊J���ڕW�́A700�`800km/L�ł����B�������A���t�������Ă̖ڕW�ł͂Ȃ��A���ۊJ�������͂���ɂ͋y�т����Ȃ��L�^�����o���܂���ł����B���̍ő�̌����͖`���Ɍf�����J�����j�ɂ���܂����B�u�t���[���̑啝�Ȍy�ʉ��v�͖��炩�ɂ�肷���ŁA�O�ւ̃A���C�����g�͋����͂Ђǂ��A�傢�ɑ�����������܂����B�܂��A�u�z�C�o���u�x�~�@�\�A��փh�O�N���b�`�̐V�݁v���A�@�\�̊����x�̒Ⴓ����Aeasy�ǂ��납�A�h���C�o�[�ɉߑ�ȕ��S�������邱�ƂɂȂ�܂����B����ɁA1996�N�x�ɐ��Z���Ȃ��܂܃G���W�����������Ă��܂������Ƃ��A�M�����̒ቺ�������Ă��܂����B�������A�������������̖��_������Ȃ�����A�����������̒ቺ�ɂ��A�x�X�Ƃ��ĉ��ǂ͐i�݂܂���ł����B
�{�i�I�ɉ��ǂɎ��g�ݎn�߂��̂́A�f�r���[����3�N���2001�N�x�̑��I����̂��Ƃł����B���ꂩ��́A�n���Ɋe���̉��ǂ𑱂��Ă��܂����B�����āA9��ڂ̏o��ƂȂ���2006�N�x�̑��ŖڕW��B�����邱�Ƃ��ł��܂����B�����ʂƂ��������悤������܂���ł����B
�t���J�o�[�h�J�E���A�X�e�����X�t���[����EG���̊O��
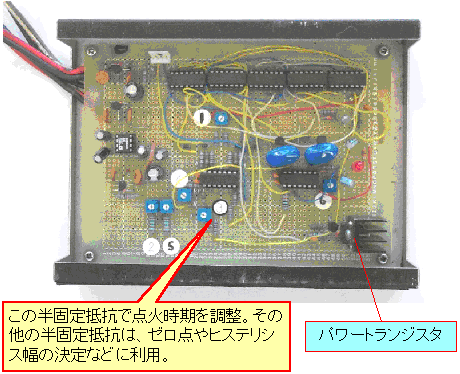
EG���ő�̔��蕨�̂ЂƂ�����B�_�Ύ��������@�\�����t���g�����W�X�^�^�_�Ή�H�ł��B�B�G���W���̉�]�̌��o��2�̃s�b�N�A�b�v�ōs���܂��B�s�b�N�A�b�v����̐M���́A75�BTDC��30�BTDC�ɓ��͂����̂ŁA����2�̐M���̊Ԋu���v������A�G���W����45߉�]����̂ɗv���鎞�Ԃ��Z�o�ł��܂��B���̏�ŁA75�BTDC�̐M�������͂���Ă��珊��̓_�Ύ����ɂȂ�܂ł̎��Ԃ����߂āA���̎��Ԃ�������p���[�g�����W�X�^��off�ɂ��ē_�v���O�ɉΉԂ����܂��B���̃p���[�g�����W�X�^�𐧌䂷��M���́A��Ƃ���2�̐ϕ���ƃR���p���[�^�ō��o���Ă��܂��B�������A�ϕ���ɓ��͂����M���̐��`��ϕ���̃��Z�b�g�ȂǕ��G�Ȏ��Ӊ�H��K�v�Ƃ��邽�߁A���i�_������ϑ����A�J�����ɂ͓���`�F�b�N�Ɏ�Ԏ��܂����B�������A�����������Ă���̓g���u�����Ȃ��A�����M�������ւ�܂����B�U��Ԃ�ƁA���̓_�Ή�H�̊J�����Ȃ���A���݂̑����d�q�����H�͂��蓾�Ȃ������ł��傤�B���̓_�ŁA�䂪���ɂƂ��ăG�|�b�N���C�L���O�ȊJ���ł����B
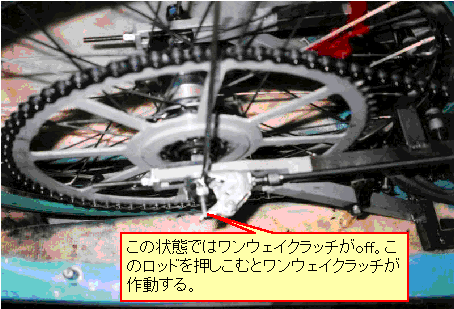
2002�N�x�̍ő�̉��Ǔ_�́A�~�V���������G�R�����p�^�C���ւ̊����ƁA���̎ʐ^�̃����E�G�C�N���b�`on/off�@�\�̗̍p�ł����B2�N�A���̃`�[���L�^�X�V�̗����҂ƂȂ�܂����B
�V�����_�փb�h�̃J�o�[�ɕ`���ꂽ�O�����̉���B���ꂪ�킪���̂����ł��B���̂����̉Ȋw�I�ȍ����͒肩�ł͂���܂��A���̂���������2002�N�x�̑��ŁA�G���W���g���u�����S���Ȃ������̂������B�`�[���L�^�X�V�̐^�̗����҂͂���Ȃ̂����H
�n���h�������ɂ���̂��A�V�^��H�̃t�����g�p�l���B�z�C�o���u�x�~�@�\�ƌ�փN���b�`�@�\����������\���m�C�h���������߁A���o�[�������āA�������肵�܂����B
���ꂪ�A�\���m�C�h�������z�C�o���u�x�~�@�\�B�����̓V�����_�w�b�h�ɗn�ڂ��ꂽ�A���~�̒���ۖ_�̐�[�Ƀ\���m�C�h���i�b�g�ŌŒ肷��ʐ^�̂悤�ȍ\���������̂ł����A�A���~�_�����U�ɂ���J�j��Őܑ�����g���u�����������A�t���[���Ń\���m�C�h���x����\���ɉ��߂đS�����ɏo�ꂵ�܂����B
�G���W���t�߂̗l�q�B��O�̍����{�b�N�X���A�_�Ύ����Ȃǂ�ݒ肷��{�[�h�B���̌�A�_�v���O�����̍�Ɛ������P���邽�߁A�ݒ�{�[�h�͍��O�ւ̌�둤�Ɉڐ݂��܂����B
��ւ̃N���b�`�@�\���\���m�C�h�����܂����B
2003�N�x����{�i�̗p�ƂȂ����d���I�C���|���v�B�R������S�ɖh�����Ƃ͂ł����A���^�]�̓s�x�A�N�b�L���O�y�[�p�[���ʏ���邱�ƂɂȂ�܂����B
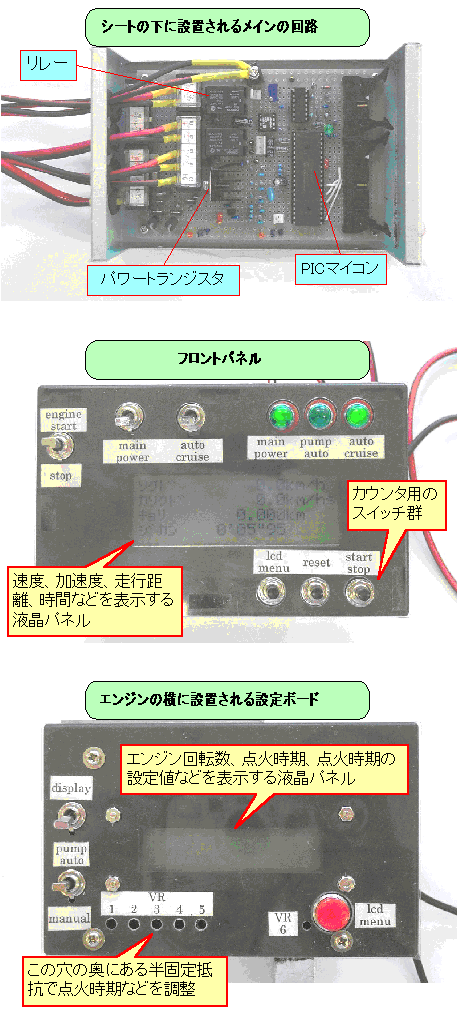
�����āA���ꂪ�V�^�����d�q�����H�B�G���W���X�^�[�g�y�уX�g�b�v�X�C�b�`�ŁA�X�^�[�^�[���[�^�A�z�C�o���u�x�~�p�̃\���m�C�h�A��փN���b�`�p�\���m�C�h�A�I�C���|���v���ꊇ���Đ��䂵�܂��B�܂��A��]���ɉ����ē_�Ύ�����ݒ�ł���悤�ɂȂ������A�ߐڃZ���T��p�����T�C�N�����[�^�@�\���L���Ă��܂��B
�V�t�g�t�H�[�N�������錊�𗘗p���Ē��Ԏ����x���邱�Ƃɂ��A�쓮�����ጸ��}��܂����B
��փX�v���P�b�g���ɕ��d���H�ŃX�v���C���a���A���̂܂܃n�u�ɛƂ߂���悤�ɂ��āA�K�^��u�������炷���Ƃɐ������܂����B
�����d�q�����H���t�����f���`�F���W���܂����B
�ۊǂ��Ă��������X�^����7�N�Ԃ�ɍ�蒼����GFRP���J�E���B�I�̃X�e�b�J�[(�G���u����)�̈Ӗ��́A�䂪���̍ō��@���ł��B
�I�����炵��������A�O�N�x�̋L�^��178km/L���X�V���Ă��܂��܂����H
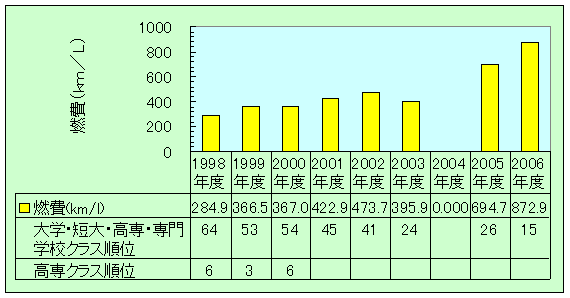
��1�D2001�N�x���A����N���X�Ƃ��Ă̕\���E���ʔ��\���Ȃ��Ȃ����B
��2�D2003�A2004�N�x�͉J�����s�B
��3�D2004�N�x�̓��^�C�A�B
�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫���Ȃ�܂�